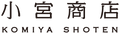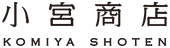日本製洋傘

日本製洋傘
JAPAN-MADE
WESTERN
UMBRELLAS
幕末に日本に伝わった洋傘は、
日本の職人技術と独自の美意識によって磨き上げられました。
その伝統を受け継ぎ、現代に息づく日本製洋傘の魅力をご紹介します。
傘の始まりと日本製洋傘
傘のはじまり
傘の由来は古代エジプト紀元前6世紀ころまでさかのぼると言われています。王の頭上へ従者が傘を差しかけられている彫刻や絵画が残されていて、傘は権威の象徴として日よけのために用いられていました。紀元前400年代にはギリシャの女性のあいだで「パラソル」が一般的になります。
さらに時代は大きく下り、1660年代にはフランスに伝わりイタリア、スペインなどで上流階級婦人たちのファッションアイテムとして流行しました。1750年頃のロンドン、ジョナス・ハンウェイが雨傘を使ったのが大きな転機と言われています。その後、傘は雨よけのもの、イギリス紳士のマストアイテムとなったと言えるでしょう。

1868年(明治元年)に創業した「仙女香坂本商店」による日傘 (関連記事)

明治後期に製造されたと思われる日傘 (小宮商店所蔵) (関連記事)
日本の和傘と洋傘
日本に洋傘が入ってきたのは、1854年のペリー来航の時と言われています。「色黒くして蝙蝠の如く見ゆ」との記録が残っていて、その所以で「蝙蝠傘(こうもうりかさ)」と呼ばれるようになったようです。
文明開化に華やかなりし時代、一部の上流階級のものだけが持てる高級品として、洋傘は輸入されていました。そこに大きな役割を果たしたのは、江戸時代より人気の白粉「仙女香」の製造販売をしていた坂本商店でした。その五代目・坂本友寿が洋傘・日傘の輸入販売をはじめ、日本における洋傘業界のパイオニアと言われています。さらに六代目を継いだ坂本友七氏はヨーロッパへ渡って洋傘・日傘の製造工程を学び、日本国内初の量産のために五年もの歳月をかけそれを果たします。
高度成長期を境に減少した日本製洋傘
そして高度成長期、小宮商店の店舗がある東京下町だけでも70以上の傘関係のお店が軒を連ね、そこには大勢の傘職人がおり、業界中が活気に満ち溢れていた時代でした。その後平成になると傘業界は多くの会社が人件費の安いアジア諸国に製造の主軸を移すことになり、日本の傘職人は多くが廃業、傘屋も倒産に追い込まれ、現在では日本製の傘を作っている傘屋は、都内でもわずか数軒となっています。
鹿鳴オンブレル
2019年、小宮商店では仙女香坂本商店のオリジナルを参考に、レプリカモデルを完成させました。当時の文献を紐解き、デザインや形、サイズに至るまで可能な限り再現しています。このレプリカモデルは「鹿鳴オンブレル」として小宮商店・東日本橋の店舗に展示販売しております。
明治時代の復刻日傘・鹿鳴オンブレル

甲州織
Koshu-ori
日本製洋傘の大きな魅力の一つは、
400年以上の歴史をもつ山梨県の伝統織物
「甲州織」を用いていることです。
富士の湧き水による発色の良い先染め糸が織りなす、
艶やかな織物の魅力をご紹介します。
甲州織のルーツと
400年を超える織物文化
「甲州織」は山梨県富士吉田市を中心とした郡内地域で作られる、400年以上の歴史を誇る織物です。そのルーツは「甲斐絹(かいき)」と呼ばれる正絹の織物です。
郡内織物産地のルーツは、およそ千年前の平安時代に施行された法令集「延喜式(えんぎしき)」文献に年貢の献上品としてその記録を見ることができます。甲斐絹そのものの起源は約400年前、いわゆる南蛮貿易によって海外からもたらされた生地をもとにして作られたものだといわれています。南蛮貿易によって輸入された織物・糸類に「海気(かいき)」と呼ばれているものがあり、それが「甲斐絹(かいき)」のルーツといわれています。
江戸時代になると郡内初代秋元泰朝(あきもとやすとも)は自らの出身地である上州から織物の技術者を招き、産業として発展させ、元禄時代には高価な織物として広く知られるようになりました。
(参考:The Kaiki Museum)

仮織をした緯糸を抜き取り、手でほぐしながら織り上げる「ほぐし織」

シャトル織機で織り上げる両面生地
先染めならではの美しい艶が特徴
伝統的に受け継がれているのは糸を先に染めてから織る「先染め」、艶のある鮮やかな糸に仕上がります。先染めで大きなポイントとなるのが、染める工程に使う水。きれいな水であるほど、発色が良くなります。長い時をかけて溶岩層を通って地表に湧出してくる富士山の湧き水の恵みを受け、深く鮮やかに染まります。そして髪の毛よりも細い極細の糸で繊細で密度の高い生地に織りあげていきます。
こだわりの「小幅」生地
反物には大きく分けて、「広幅」「小幅」の二種類があります。「広幅」は生地幅が120〜130センチ程度、「小幅」とは生地幅が60センチ程度の幅が狭い生地です。これは傘専用とも言え、親骨のサイズに合わせたもの。そして小幅の織物は昔ながらの「シャトル織機」を使っているのが特徴です。シャトルと呼ばれる器具が往復を繰り返して、一本続きの緯糸を経糸に通していく方式を採用しています。つまり、緯糸は切れることなく、ずっとつながったまま織られていくことが大きなポイントです。
ほつれることがないので、傘の縁はミシン目がなく、シャープでとても洗練された仕上がりになります。
このシャトル織機を使って傘生地向けの小幅の織物を作っている工場があるのは、今では山梨県を残すのみとなっています。

縁にミシン目がない「小幅」生地を活かしたデザインが魅力の 「Two Ply」シリーズ

甲州織のできるまで
山梨県富士吉田で、昔と変わらぬ多くの分業工程を経て作られる甲州織。機屋さん、染色屋さん、整経屋さん、付け屋さん、整理屋さんなど、たくさんの職人の手を経て完成する製作工程をご紹介いたします。
甲州織のできるまで「二つ折り」折り畳み傘
Two Fold Umbrellas
日本製の折り畳み傘は、親骨が外側に折れるタイプの骨を多く採用してきました。小宮商店では、創業から現在までの長い間、この「二つ折り」にこだわって傘づくりを続けてきました。シルエットが美しく、甲州織や天然素材の上質な生地と相性が良い「2つ折り」折り畳み傘の魅力をご紹介します。
小宮商店がこだわる、「2つ折り」折りたたみ傘の魅力