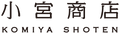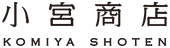光沢感のある奥深い色合いと、重厚感のある上品な質感
山梨の先染め織物「甲州織」
400 年以上の歴史を誇る甲州織は機(はた)屋さん、染色屋さん、整経屋さん、付け屋さん、整理屋さんなどのたくさんの人の手を経て完成します。

甲州織のできるまで
小宮商店の人気シリーズ「Two Ply」をはじめ、小宮商店の傘を作るのにかかせない甲州織の傘生地。その傘生地のほとんどが、山梨県富士吉田周辺で、昔と変わらぬたくさんの分業工程を経て織られています。
1. 染色屋
染色屋で織る前に糸を染めます。(先染め)
綛(かせ)と呼ばれる状態の糸の束を高圧蒸気を使用して染めます。

綛(かせ)

この小さな穴から布地を染める染料(分散染料)が出ます。

染料を配合して綛を窯で染め上げます。

このように甲州織で使用される糸は染色屋さんの経験と知見によって見事に染め上げられていきます。
2. 整経屋
整経屋さんでは、染色した糸を経糸として整えます。
「かせ」状の糸をボビンに巻き取り、さらにボビンの糸を織物の幅や長さ、配列などに合わせて、ドラムに巻いていきます。

この時に均一の張力で巻き取ることが重要で、整経によって織機にセットできる状態にします。
3. 機屋(はたや)
機屋(はたや)さんでは、先ほど整えた経糸に緯糸を織り込み、シャトル織機で織物に仕立て上げていきます。

小幅のシャトル織機は大変希少な織機で、緯糸をシャトルで打ち込み、折り返しながら織っていくため、生地の端にミミが出来上がります。大きい生地を傘の幅に合うように縫う必要がないため、ミシン目もなく見た目もスマートで、スタイリッシュに見えるのはもちろん、長くご愛用いただいてもほつれる心配がないことも魅力のひとつです。

4. 整理屋
最後に、整理屋さんで反物に撥水・耐水加工を行います。
こうして、今では希少となってしまった傘専用の甲州織はたくさんの工房、たくさんの職人達の手を経て、やっと小宮商店に傘生地となってやってきます。
滲んだ表現が美しい、染型で先染めする「ほぐし織」

ほぐし織の製法


仮織した経糸に一色ずつ捺染型を当て、色を丁寧に重ねて染めた後、小幅のシャトル織機にセットした緯糸を打ち込み、本織をしていく織り方を「ほぐし織」といいます。 仮織された経糸に捺染型を当て、捺染台で絵柄を付けていくという作業が加えられます。

本織をする際に、仮織をした緯糸を抜き取り、糸を手でほぐしながら織り上げるので、染めた模様が微妙にずれ、水彩画のようになるのが特徴です。プリントとは一味違う、あたたかみのある柔らかい表情をお楽しみください。

このように、たくさんの人の手を経て出来上がった生地を職人が裁断し、縫い合わせて傘に仕立てていきます。