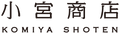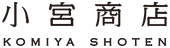語り:石井健介(職人・技術指導)
シリーズ 『語り継がれる想い』
第1話 – 創業者・小宮寶将の肖像 –
第2話 – 2代目社長・小宮武との出会い -
第3話 – 激動する市場の中で、「小宮商店の洋傘」が形となる -
前回お話ししたように、私が小宮商店に入社し、小宮武のもとで働きはじめたのは昭和49(1974)年。
昭和50年代に入ると社員は少しずつ増えはじめ、役員を含めて7人の会社となりました。
小宮商店は個人商店から会社組織へと変わり、2代目・小宮武を中心とした“新小宮丸”はさらなる成長に向けて新たな船出をすることになりました。

2代目社長・小宮武
社内の組織体制を整える一方で、国内の市場もすごい勢いで変化していました。
傘専門店の売上が大幅に減少する一方、銀座の小松屋や阿波屋といった履物屋さんの売上が順調に伸びていきました。 小売店から量販店へとターゲットを切り換えながら、よりファッション性が高いメンズ洋品市場の開拓に力を入れました。
そのためには細部に至るまで徹底的にこだわった、本物志向の洋傘を制作する必要がありました。
傘の本場といえばイギリス。 そして、その真骨頂は「コウモリ傘」と呼ばれるシルエットにこだわったメンズ傘です。 それまで私たちが作っていた洋傘よりも「深張り」で、たたむと細身でスタイリッシュな洋傘です。 張りが綺麗なことがとても重要でした。
試行錯誤のすえ、たどり着いた形
張りを綺麗にするために生地を引っ張り過ぎると、使いづらい傘になってしまい、その調整はとても難しい作業でした。
職人たちは試行錯誤を繰り返し、生地を裁断する際の木型のカーブを調整することで、シルエットが綺麗で、同時に使いやすい傘を作れるようになっていきました。

のちに伝統工芸士となる職人・菅澤勝美
小宮商店は創業以来、骨の関節部分を布で包む「ダボ巻き」や、受骨を束ねた箇所を生地で包んだ「ロクロ巻き」など、日本の洋傘作りの様式美を追求してきました。 そこにシルエットの美しさや使いやすさが加わり、現在の「小宮商店の洋傘」のスタイルが出来上がっていきました。
この頃、私たちと同様のこだわりを持った、横浜の『小島商店』と協力関係を結びました。
小島商店の店主・小島昭二さんは、横浜元町にあった傘専門店『伊勢勘』の流れを汲む名職人で、独特の型をもつ、美しいシルエットへのこだわりは業界随一でした。
1985年頃、小宮商店の職人は小島氏の引退を受けて、『丸善』や『信濃屋』の洋傘の制作を引き継ぐことになりました。 上質なメンズファッションのスタイルを追求するブランドに刺激され、小宮商店の洋傘もさらに洗練されていくこととなりました。

小宮商店の歴史を語る石井健介
シリーズ 『語り継がれる想い』
第1話 – 創業者・小宮寶将の肖像 –
第2話 – 2代目社長・小宮武との出会い -
第3話 – 激動する市場の中で、「小宮商店の洋傘」が形となる -