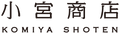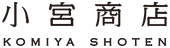幕末から始まる、日本の洋傘業界の歩み
日本人が初めて洋傘と出会ったのは、1854年(安政元年)に開国を求め和親条約締結のため米国のペリー提督が黒船で浦賀沖から上陸した頃から始まります。 当時は黒色の洋傘の形状から蝙蝠傘(こうもり傘)と呼ばれていた江戸時代、幕末のことです。
日本製の洋傘は、1868年(明治元年)から輸入洋傘の販売を手掛けてきた「仙女香坂本商店」が4年後に初めて作り上げています。 その歴史の始まりは、1872年(明治5年)まで遡ります。

幕末の江戸城本丸で洋傘(こうもり傘)を差す武士の姿 (『日本洋傘の歴史と名鑑』より)
-
1868年(明治元年)
「仙女香坂本商店」は、いち早く西洋化の文明商品である輸入洋傘を取り入れ販売を開始しています。

仙女香坂本商店 (『東京写真帖』より)
-
1872年(明治5年)
「仙女香坂本商店」は、輸入洋傘の販売経験から400年の歴史をもつ甲州織の「甲斐絹」を洋傘生地に改良し、輸入傘を分解した部材を使用して初めて日本製の洋傘を作りあげています。 また、同年に輸入雑貨を扱っていた上村彦次郎氏も輸入洋傘販売を始めています。 その後、英国から洋傘部材を輸入し甲州織の「甲斐絹」を使用して洋傘を作りあげています。
-
1887年(明治20年)
「仙女香坂本商店」6代目の坂本友七氏は、5年間仏国のパリで洋傘の製法や流行を研究して明治24年に帰国しています。
-
1890年(明治23年)
洋傘骨の鋼材に焼き入れが可能となり洋傘の純国産化が開始された年です。

明治中期の洋傘店 (『洋傘ショールの歴史』より)

鹿鳴館時代の舶来洋傘 (『洋傘ショールの歴史』より)
-
1894年(明治27年)
明治天皇の銀婚式の献上品には、東京洋傘同業組合から天皇陛下用には、仙女香の坂本友七氏から紳士洋傘が謹製され皇后陛下用には洋傘商の上村彦次郎氏から婦人洋傘が謹製され同時に献上されています。 当時の技術の高さと意匠表現技法は、輸入洋傘に勝るとも劣らない高品質の製品に仕上げられており現在に引き継がれています。
-
1895年(明治28年)
洋傘骨商の河野寅吉氏が、1868年に英国のフォックス社で開発されたU字断面の溝親骨製造に成功しています。 これにより洋傘骨の純国産化が達成され、現在も基本的な構造や製法が受け継がれています。
-
1899年(明治32年)
さらに河野寅吉氏は、スエーデン製の圧延した鋼鉄リボンをU字型に曲げて焼き入れに成功しています。 当時製造されていた洋傘骨で加工された明治後期の懐かしい絹素材使用の洋傘は、東日本橋にある小宮商店のショップでご覧いただけます。

明治時代の傘 河野寅吉による骨を使用 小宮商店所蔵

明治後期に流行した琥珀縁レースの日傘 (『日本洋傘の歴史と名鑑』より)

明治時代 紳士用洋傘(『三越タイムス』明治44年より)
-
1912年(大正元年)
大正時代は西洋文化の影響を受けた新しい文芸・絵画・音楽・演劇などの芸術が流布して花開いた時代です。 洋傘分野では、日傘が伝統工芸品として価値が高められた時代でもあります。 生地では、着尺の絹織物や染め物に西洋の技術が生かされたレースや刺繍が組み合わされた物、また洋傘手元(持ち手)では、象牙・鼈甲の彫刻物や蒔絵・螺鈿・彫金等職人の細工ものが数多く手掛けられています。

大正時代の洋傘 (『三越タイムス』大正2年より)

大正10年頃のレース加工日傘 (『日本洋傘の歴史と名鑑』より)

大正時代初期の象牙、螺鈿、彫刻の日傘用手元(持ち手) (『日本洋傘の歴史と名鑑』より)
-
1926年(昭和元年)
昭和の時代は、女性の社会進出が広がり活躍する場が確実に根ずき始めた時代です。 洋傘の製造も拡大され、輸出の花形商品に成長する時代でもあります。
また、昭和の中頃には、折りたたみ骨の開発が進められ、2段中棒のホック式や3段中棒のコンパクトタイプ、さらに小型軽量化の波に乗り多段式のミニ骨が登場しています。

昭和初期のほぐし織の晴雨兼用傘 (『日本洋傘の歴史と名鑑』より)
-
1930年(昭和5年)
小宮商店の創業者小宮寶將は、自身の出身地である山梨で明治の始めから織り続けられている洋傘生地である甲州織の小幅先染「甲斐絹・かいき」を使用して東京都中央区の浜町で洋傘の製造販売を始めており、現在に引き継がれています。
-
1941年(昭和16年)
日本は、太平洋上で米英との開戦が始まるなか昭和18年の戦時統制令により洋傘業界も企業の整備統合や廃業で縮小の状態となっています。
-
1945年(昭和20年)
日本は、無条件降伏で終戦を迎え洋傘業界も戦後の再スタートで新たな活動が開始されています。
-
1949年(昭和24年)
中棒がスライドする独国のクニルプス製折りたたみ洋傘を参考に開発が進められ製品化されています。 同年に洋傘ショール商工協同組合が設立され現在に至っています。
-
1951年(昭和26年)
折たたみ傘の改良が進み親元骨に溝地金が使用されることにより先親骨と元親骨が固定されるホック式が開発されています。 これが現在の日本式折りたたみ骨の原型になっています。
-
1953年(昭和28年)
防水性が高く低価格のナイロン生地が登場することにより、画期的に折りたたみ傘の需要拡大につながっています。
-
1954年(昭和29年)
折りたたみの改良がさらに進み、親元骨にスプリングが組み込まれ先親骨と元親骨の開閉自在のものが登場しています。
-
1960年(昭和35年)
輸出専用に製造されていたジャンプ式長傘の国内販売が開始されています。 また同年には、「テトロン商標」の品質が安定し強靭なポリエステル生地が開発され、今日の洋傘業界の基礎が出来上がったのはこの頃です。
-
1963年(昭和38年)
全国の洋傘製造業者の有志により日本洋傘振興協議会(JUPA)が設立され現在に至っています。
-
1964年(昭和39年)
戦後18年、日本の東京で初めてオリンピック競技大会が開催され世界の仲間入りを果たしています。
-
1965年(昭和40年)
日本の洋傘は、生産量世界一(4,320万本)、消費量世界一(3,240万本)、輸出量世界一(1,028万本)の三冠王を達成と毎日新聞(昭和41年9月2日版)で報道されています。 この頃には、折りたたみ傘の小型化が進み中棒も二段から三段のコンパクトタイプに改良されています。また、中棒や骨部材にアルミ軽合金が使用され小型軽量化の波に乗りミニ傘も販売され洋傘の品種の基本が出揃っています。
-
1970年(昭和45年)
芸術家岡本太郎の太陽の塔で象徴される大阪万国博覧会が開催され、万博傘と称される手元(持ち手)操作で開閉する長傘が登場しています。
-
1972年(昭和47年)
仏国オートクチュール・ブランドのピエール・カルダンとの国内初のライセンス・ブランド洋傘の登場を契機にイヴ・サンローラン、クリスチャン・ディオール、ニナ・リッチ等の著名ブランド洋傘が有名百貨店・専門店で販売展開されています。
-
1980年(昭和55年)
この頃には、ソニア・リキエル、エマニエル・カーン、高田賢三を中心としたプレタポルテ・ブランドからバーバリー、ダックス、アカスキュータム等のハウス・ブランドが加わり、さらにDC・ブランドへとライセンス・ブランドが拡大され一世を風靡した時代です。 高度な生産技術と感性を併せ持つ指導の下に生産基地も韓国に移り、さらに台湾に移っています。
-
1989年(平成元年)
昭和の天皇制から平成の象徴天皇制の時代です。 洋傘の生産基地も台湾から主力が中国に移り始めている時期です。
-
1990年(平成2年)
高度成長期のバブルが弾け始めた時期であるが主力生産基地の中国からの輸入数量は、毎年1億2千万本前後の実績が維持され安定した製品輸入がされています。中国の製造業が担ってきた経済成長の背景には、長年にわたる環境汚染の問題が挙げられます。 また日本国内でも公害問題で透明ポリ塩化ビニル傘の使い捨てが大きな社会問題となっています。
-
2009年(平成21年)
この年には、洋傘業界にも環境問題に配慮した洋傘として部材が簡単に分解でき焼却できるものと再利用できるものとに分類できる新製品の「エコロジー洋傘」が開発されたが、風圧に弱いため成果につながらず自然消滅しています。
-
2010年(平成22年)
世界の生産工場として国内総生産GDPが二桁成長してきた中国も、北京オリンピックの2008年頃から減速を辿り始めています。 経済特区で運営している洋傘生産工場も人件費の高騰や人手不足の影響を受け安定生産が難しくなり始めた頃です。
-
2016年(平成28年)
中国の国内総生産もこの頃には、7%を維持することも困難な状況になっており年度末の集計結果では、6.7%の実績報告になっています。 一貫工程 の洋傘生産工場は、工程別に細分化された工場となり最盛期の1/10位の規模に縮小されています。 すでに、低価格のポリ塩化ビニルの透明傘の製造は、中国からカンボジアに生産基地が移動しはじめています。 また、中国から日本向けの洋傘の輸出数量・金額ともに前年実績対比20%程度減少しています。
-
2017年(平成29年)
国際的な東京オリンピック・パラリンピック競技大会を3年後に控え海外からの観光客が年々増加の傾向にあり観光の目的も大きく変化しています。 日本人を含めて新たに、日本の自然、歴史、伝統文化との触れ合いや日本製の洋傘を含む手作りの伝統工芸品への関心が高まっています。
-
2018年(平成30年)
150年近くの歴史と伝統技術を引き継ぐ東京洋傘が「東京都伝統工芸品」に認定されています。 現在、東京洋傘を含む日本製の傘の製造は平成20年度比で1/2の約66万本であるが加工職人の高齢化による後継者の育成と製品加工に必要な部材調達網の見直しが大きな課題になっています。

東京都伝統工芸品に認定された「東京洋傘」。 絹を使用した小宮商店の甲州織・裏縞
-
2019年(平成31年)
東京の風土と歴史に育まれ、時代を超えて受け継がれた技術で長年東京洋傘を作り続けてきた職人8名が「東京都伝統工芸士」に認定されています。 小宮商店からは、熟練職人の小椚正一氏と菅澤勝美氏の両名が認定され日々高度な技術の傘作りと後継者の育成に努めています。
-
2020年(平成32年)
小宮商店は明治時代に仙女香によって作られた西洋日傘を参考に『懐古版・鹿鳴オンブレル』を製作する。 様々な分野の職人の技術を集結し、当時の日傘の美しい姿の再現する。